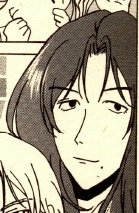
■しろばんばのおぬい婆さんが辰之助を失ったのは、40代以降だろうと思います。30代で医師としての栄職を離れ、地元に帰った辰之助がおぬいに出会ったのはその頃だとすれば、おぬいは20歳くらいだったかもと思います。
若かったおぬいから時間を奪った代償として、かなりの資産を置いて行く辰之助ですが、彼女の方も40歳を越えて次の旦那を見つける事は無理だったと思います。
19歳でルーザー様を失った高松に、次の人生はなかったのかと思いました。ガンマ団に関わった時点で、選べる道は消えていたかもしれませんが、44歳くらいで好き勝手出来た?なら、若かった高松には無限の可能性があったと言えます。
当時の高松の頭の中には、シンタロー(キンタロー)の行く末を、なるべく近くで見届けたい思いしかなかったのだろうと思います。キンちゃん出現後は、離れていても繋がっている自覚でも芽生えたのか隠居しますが。自分は強情な人が好きです。
■読む時間がないまま、林芙美子の浮雲を鞄に入れています。恐ろしい事に本の裏に「義弟との不倫から逃げ、インドシナに向かった」と書いてあります。暗夜行路の時も「母の不義、妻の不義に悩み」と華々しくネタバレがありました。
ネット等であらすじが読める事も多いので今更ですが、読んでみないと本は分かりません。暗夜行路も、母や妻の不義そのものに悩み苦しむと言うより、母の場合はかえって祖父への愛情がわき、妻の場合は自分の内面との戦いへ突入していった観があります。
よく言えないのですが、本を読む時は、作家さんを信じるしかありません。どの本だって完成に行きつく前に書いた方は苦闘したでしょうし、長い年月を越えて出会った本は信じるべきです。
だから、あらすじだけで想像をたくましくするのは余り愉快ではありません。自分の好みのせいなのか、
「門」 友人の妻との不義が主人公を苦しめる
「それから」友人の妻が欲しくてならない
「行人」自分の妻が不義を働くのを願っている
「明暗」妻より大事な女性に会いに温泉に行く
漱石の頭の中が心配になるラインナップですが、本懐はあらすじにあるのではなく、読んで初めて分かるのだと自分は信じます。つまり、読まないと分からないのです。
■本が読みたいです。タイトルだけ聞いて、なんとなくあらすじはネット等で知っているけど全体を知らない作品が多いです。
学生の頃、芥川や太宰を一気読みしようとして、ライトな作品はよかったけれど、段々ヘビーな方を開いて行くと辛くなった事があり、読んでみないと分からないと思った事があります。芥川だけは、ものすごく有名な作品でも、涙も出ないくらい辛い内容のものが多い印象です。太宰もそうかもしれません。
全国津々浦々、文豪が愛した温泉、山、森は多いですが、各作家さんの作品を理解したと思えるまで踏破する事は稀かもしれません。旅を愛した文豪は多く、志賀、漱石、田山花袋、与謝野夫妻、康成、と興味があって紀行文をいくつか開いてみましたが、一朝一夕に読める量ではなかったです。
そう思うと、ほぼ江戸と呼ばれたエリアに舞台を集中させた漱石。関西文化を愛しながら、根っこは短気でいなせな江戸っ子だったろう谷崎、純粋なる東京人であった荷風は分かりやすいと思います。
志賀は何故鳥取に向かったか、尾道に向かったかなんて、卒論でも書かないなら考えなくていいのだろうと思います。 |
|