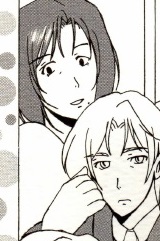
・康成をゆっくり読んでいます。読みやすいかなと思って手を出した掌の小説、読みやすいと言えば読みやすいし、読みにくいなと言えば大変読みにくいです。
以下雑感です
・踊り子ってなに?
伊豆の踊子だと=旅芸人の一家、一座の少女でいいと思うのだけど(こち亀であったような)
浅草の踊子、というと分からない。イメージ的には、舞姫のエリスなのかなと思う。あんまり清らかな感じはしない。伊豆の踊子でも「踊り子が性接待させられるかも」と心配する描写がある。
(※関東大震災前は、浅草に劇団があって・・・というらしい 康成、日本の美の代表みたいに言われるけどモダンじゃないか?)
・劇中、結構上流・中流の人が多いよね?
康成なので、あんまり貧しい家は出ない気がする。親戚関係も、荷風や谷崎程もめていないし、基本的に生涯お金持ちなのが康成だったのでは
・時代設定がそもそもとびとび
康成の活動期間は 1919〜1972年
漱石が亡くなった直後くらい〜上越新幹線着工くらい
結構長い 雪国が1935年(在来線・上越線開業が1931年)なのだから、いつの間にか新潟〜東京に高速鉄道が走っている(まだ着工されただけ)!
関東大震災(1923年)、第二次世界大戦(1941年真珠湾攻撃)、と天地がひっくり返る様な時代だった
谷崎程口数が多くなく。荷風ほど筆まめでもなく、漱石程「どこにでもある話 結婚の話が多い」という程でもなく。寡黙な感じで延々書かれると、時代設定を思い出すのが大変
小説読むのに時代なんて関係ないじゃんと言いたいところだけど。拓海のハチロクだって、キンコンなったじゃん・・・というくらい時間の流れは作品と密接 |
|